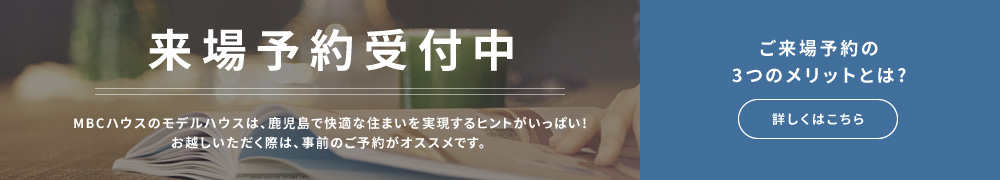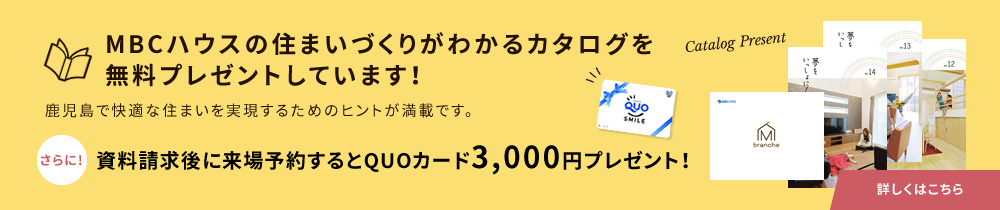TEL
099-226-7777
受付時間/9:00~17:00 定休日/水曜日(祝日除く)
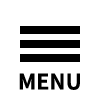
スタッフブログ
Blog
2020.03.23
「住宅におけるオフグリッドと、新しい社会インフラの構築」
設計課の山下です。 ( 3月になっても初夢の続きで恐縮ですが…。)
昨今、ソーラーパネルと蓄電池の普及によって、「オフグリッドの家」の考えが提案されてきています。「オフグリッドの家」とは電気において、電力会社の送電網と接続せず、ソーラーパネルや蓄電池などで電気を供給し、電気に関し自給自足する家のことです。
そこで今日は、先日みた「社会インフラの危機」というテレビ番組を契機に、オフグリッドの考え方を、新しい社会インフラの構築に利用できないか、夢見てみました。
テレビの報ずるところによりますと、
高度成長期の昭和30年代後半から、昭和末までの高度成長期に造られた、水道、下水、橋梁などの社会インフラが時間の経過とともに老朽化し、その改善が喫緊の課題となっているそうです。劣化による水道管の漏水や下水管などの断裂であり、それらを改善する為に、新規の社会インフラの構築にも似た莫大な費用が掛かり、財政困窮の折、社会問題となっているのだそうです。
そこで、電気に関するオフグリッドの考えを、既存インフラの改善に役立てられないか考えてみました。すなわち、エネルギー面における、既存のインフラと住宅との切断です。もちろんすべての既存社会インフラとの切断は合理的でもないでしょうが、発展する技術を生かしたスマートな社会インフラに転換することは一考の価値があるのではないでしょうか。
アフリカの電気・電話事情で言えば
例えば、アフリカの発展途上国等においては、社会インフラの一つである水道や電気、電話に関し、従来の先進国がしてきたような水道網や送電線、電話網等の固定インフラを整備してから、水道や電気、電話を普及するのではなく、井戸や、ソーラー発電、電波の発信基地局による整備で水道、電気、携帯電話が普及しています。
つまり、技術の進歩によって先進国とは異なる方式で電気や電話が普及しているのです。
このことから見えてくることは、社会インフラは、新しい時代の新しい社会インフラに向かうのではないかということです。それは、全体と個の役割分担、もしくは全体から個への流れです。旧来の社会インフラが大量、画一、集合、一括、とすれば、新しい形の社会インフラは個別の実情にあったインフラです。
現代社会において全体から個への流れは、既にエネルギーに限らず、5Gを使った配車における地方の公共交通網整備や、個々人の体質に基づく薬の投与、福祉、等々、様々な分野にその芽生えはあります。
住宅に関する仕事をしている我々にとっても、住宅に関係する新しい社会インフラとはどのような方向に行くのか、そして住宅のオフグリッドとはどのようなものなのか、とても興味あることです。
電気に関して言えば、先に述べたように、細かいインターフェイス等の問題はありますが、個別のソーラー発電と蓄電池、地域でのエネルギーの融通ですでにほぼその技術上の基本システムが出来上がっています。小売り大手のイオンなどは全事業の電気エネルギーを自己の創出と地域に密着した融通の協力関係のシステムで賄おうとしています。
水道と下水に関しても、その技術的可能性はあると思っています。例えば、水道に関して言えば、水の種類として上水、中水、下水があり、下水に関して言えば、現在建築基準法による放流の制約はありますが、「浄化槽」という基礎技術はあります。しかも発生する汚泥のメタンを利用して水素を生産しそれらをもとに発電する技術もすでにあるのです。
上水や中水に関しても、日本には海水淡水化技術や緊急災害造水器等の真水を生産する技術があり、日本の水処理技術を使えば、雨水や地下水を上水に変えたり循環使用することは容易いことです。
先のテレビ報道によりますと、今日、日本は、発電のために、化石燃料を年間18~19兆円も輸入しているそうですが、再生可能エネルギーには、日本全体の総需要量の1.8倍もの発電のポテンシャルがあるそうです。エネルギーを地産地消することが可能ならば、これらのお金が浮く可能性があります。
ただし今までは、再生可能エネルギーの生産コストの面がありました。しかしこの問題も、技術の革新により、最初のころの生産コストの1KWhあたり30円ぐらいから、石炭火力の12円より安い7円代までに下がる可能性があり、既に一部の先進的ヨーロッパでは7円代となっているそうです。 日本は久しく資源小国であると言われていましたが、見方を変えれば資源大国となりえます。
住宅に関する仕事をしている我々も、このような流れに貢献したいと思っており、それは持続可能性という意味で、SDG`sの思想ともつながります。ZEH、LCCM住宅の推進も、これらの一環です。新しい社会インフラの取り組みに興味をお持ちの方は、是非、我々にお声かけしてください。完全なるオフグリッドの家はコストの面から、まだ、端緒ではありますが、来るべき未来に寄与する近未来の住宅を一緒に考えていきたいものです。
初夢の続きとして話をすれば、もしかしたら、住宅の基礎中空間がエネルギーに関する基地となる可能性があります。これから新しい地下空間の時代が来るかもしれません。
昨今、ソーラーパネルと蓄電池の普及によって、「オフグリッドの家」の考えが提案されてきています。「オフグリッドの家」とは電気において、電力会社の送電網と接続せず、ソーラーパネルや蓄電池などで電気を供給し、電気に関し自給自足する家のことです。
そこで今日は、先日みた「社会インフラの危機」というテレビ番組を契機に、オフグリッドの考え方を、新しい社会インフラの構築に利用できないか、夢見てみました。
テレビの報ずるところによりますと、
高度成長期の昭和30年代後半から、昭和末までの高度成長期に造られた、水道、下水、橋梁などの社会インフラが時間の経過とともに老朽化し、その改善が喫緊の課題となっているそうです。劣化による水道管の漏水や下水管などの断裂であり、それらを改善する為に、新規の社会インフラの構築にも似た莫大な費用が掛かり、財政困窮の折、社会問題となっているのだそうです。
そこで、電気に関するオフグリッドの考えを、既存インフラの改善に役立てられないか考えてみました。すなわち、エネルギー面における、既存のインフラと住宅との切断です。もちろんすべての既存社会インフラとの切断は合理的でもないでしょうが、発展する技術を生かしたスマートな社会インフラに転換することは一考の価値があるのではないでしょうか。
アフリカの電気・電話事情で言えば
例えば、アフリカの発展途上国等においては、社会インフラの一つである水道や電気、電話に関し、従来の先進国がしてきたような水道網や送電線、電話網等の固定インフラを整備してから、水道や電気、電話を普及するのではなく、井戸や、ソーラー発電、電波の発信基地局による整備で水道、電気、携帯電話が普及しています。
つまり、技術の進歩によって先進国とは異なる方式で電気や電話が普及しているのです。
このことから見えてくることは、社会インフラは、新しい時代の新しい社会インフラに向かうのではないかということです。それは、全体と個の役割分担、もしくは全体から個への流れです。旧来の社会インフラが大量、画一、集合、一括、とすれば、新しい形の社会インフラは個別の実情にあったインフラです。
現代社会において全体から個への流れは、既にエネルギーに限らず、5Gを使った配車における地方の公共交通網整備や、個々人の体質に基づく薬の投与、福祉、等々、様々な分野にその芽生えはあります。
住宅に関する仕事をしている我々にとっても、住宅に関係する新しい社会インフラとはどのような方向に行くのか、そして住宅のオフグリッドとはどのようなものなのか、とても興味あることです。
電気に関して言えば、先に述べたように、細かいインターフェイス等の問題はありますが、個別のソーラー発電と蓄電池、地域でのエネルギーの融通ですでにほぼその技術上の基本システムが出来上がっています。小売り大手のイオンなどは全事業の電気エネルギーを自己の創出と地域に密着した融通の協力関係のシステムで賄おうとしています。
水道と下水に関しても、その技術的可能性はあると思っています。例えば、水道に関して言えば、水の種類として上水、中水、下水があり、下水に関して言えば、現在建築基準法による放流の制約はありますが、「浄化槽」という基礎技術はあります。しかも発生する汚泥のメタンを利用して水素を生産しそれらをもとに発電する技術もすでにあるのです。
上水や中水に関しても、日本には海水淡水化技術や緊急災害造水器等の真水を生産する技術があり、日本の水処理技術を使えば、雨水や地下水を上水に変えたり循環使用することは容易いことです。
先のテレビ報道によりますと、今日、日本は、発電のために、化石燃料を年間18~19兆円も輸入しているそうですが、再生可能エネルギーには、日本全体の総需要量の1.8倍もの発電のポテンシャルがあるそうです。エネルギーを地産地消することが可能ならば、これらのお金が浮く可能性があります。
ただし今までは、再生可能エネルギーの生産コストの面がありました。しかしこの問題も、技術の革新により、最初のころの生産コストの1KWhあたり30円ぐらいから、石炭火力の12円より安い7円代までに下がる可能性があり、既に一部の先進的ヨーロッパでは7円代となっているそうです。 日本は久しく資源小国であると言われていましたが、見方を変えれば資源大国となりえます。
住宅に関する仕事をしている我々も、このような流れに貢献したいと思っており、それは持続可能性という意味で、SDG`sの思想ともつながります。ZEH、LCCM住宅の推進も、これらの一環です。新しい社会インフラの取り組みに興味をお持ちの方は、是非、我々にお声かけしてください。完全なるオフグリッドの家はコストの面から、まだ、端緒ではありますが、来るべき未来に寄与する近未来の住宅を一緒に考えていきたいものです。
初夢の続きとして話をすれば、もしかしたら、住宅の基礎中空間がエネルギーに関する基地となる可能性があります。これから新しい地下空間の時代が来るかもしれません。